「箸はいのちの橋渡し」箸づくり一筋にかける、江戸木箸大黒屋の想い

「橋は場所を結ぶもの。箸は食材と人を結ぶもの。箸も橋渡しなんですよ」
そう話すのは、江戸木箸大黒屋の創業者であり、今も箸をつくり続ける職人の竹田勝彦さん。食器の問屋に勤めていたという竹田さんは、食器を持って全国を歩き回り、販売することを20年間続けてきました。
その中で感じたことは、お箸は食器の中では目立つものではなくて端の方に置かれているもの。それでも、どんなに地方に行っても景気が悪くても、箸は必ず買ってくれる人がいるということでした。
箸は、形はみんなだいたい同じで、色や模様で選ばれる。でも、箸は口に入る大切なもの。道具として使いやすい箸がもっとあるはずだ、と竹田さんは考えるようになったといいます。
「箸は靴と同じ。自分専用のもの。その人に合った箸を使うということが大切なんじゃないか。道具というのは、高い安いではなく、自分にちょうど良いものが良いものです。人それぞれに合ったもの、ちょうど良いサイズのものをつくってみたいと思うようになりました」
そうして、竹田さんは会社を辞め、自分の手で箸をつくることを始めました。


竹田さんのつくった箸を手に取ると、その言葉どおり、「ピタッ」と手にハマるような感触があります。箸は五角形・七角形・八角形など、さまざまな形があります。
つくる工程を見せていただくと、四角形 の棒状のものが、なんの印もなしに、職人の勘だけであっという間に均一な多角形に削られていきました。

中でも、大黒屋の箸の特徴となるのは7角形のお箸。
「実は七角形というのは非常に難しいんです。つくり出すのに3年ほどはかかりました」
七角形の形には、箸に対する竹田さんのこだわりの思いがありました。
人間の指は奇数でできていて、箸を持つのは3本の指。それで、奇数の形が良いのではないかと考えたと言います。
「八角形は円に近いから柔らかく持てる。七角形は指にピタッとハマる感じがあります。自分の手で持ってみて、使いやすものを選んでもらえれば」と、竹田さん。
竹田さんが削った箸は、長野県に送られ、女性の漆職人の手によって3回ほど上から漆がかけられます。光りすぎないように刷り込まれ、水捌けの良い、使いやすい箸となります。

削られたばかりの漆を塗る前の箸

そして、江戸木箸大黒屋の箸は、修理をしてもらえることも大きな特徴です。
「機械と違うのは、人間のつくったものは、修理ができるということです。それが手作りの良さ」と、竹田さん。
大黒屋の箸の材料となる「紫檀」や「黒檀」という木は非常に貴重なもの。東南アジアで産出される銘木で、今は輸出に制限がかかってしまい、手に入りにくくなってしまいました。材質が硬く、箸をつくるのに適した木だと言います。価値のある材料でつくっているものだから、ずっと使い続けてもらいたい。壊れたら捨ててしまうのではなく、修理し続けながら、自分に合った道具を使い続けるということが大切なこと。
大黒屋さんの箸は一度使うとファンになる人も多く、年末の頃には修理の依頼も200本ほどになるとか。職人が丁寧に修理をしてくれて、また使いやすい箸になって戻っていきます。

「毎日使い続けたいというものをつくっていきたい。使ってみるほどに、『良いな』と思われるようなものをつくっていきたい」
一つ一つ、職人が想いを込められながら手でつくられる箸は、一生ものの道具です。
生きていくことに最も大切な、食べること。
その食べるための道具として、お箸も大切に選び、使い続けていただきたいと思います。
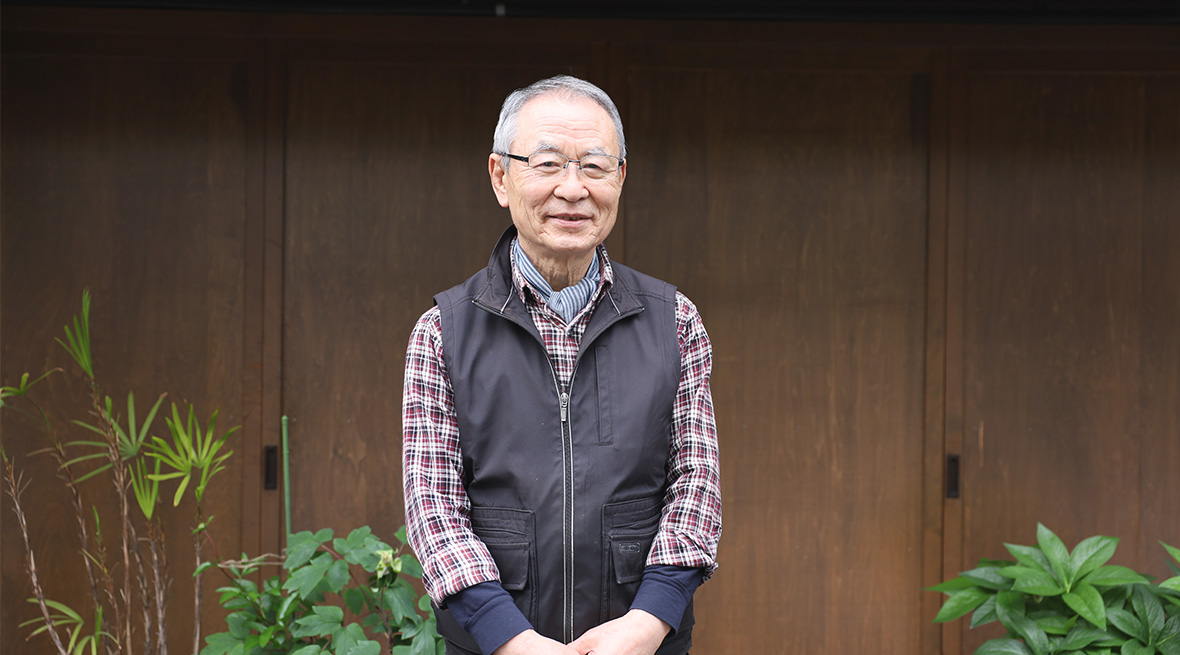
文・撮影:さとう未知子

